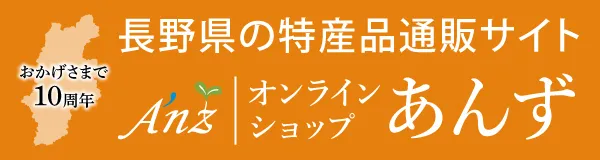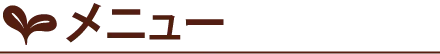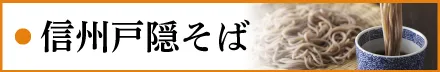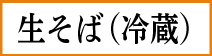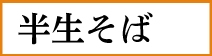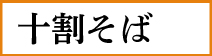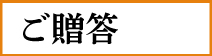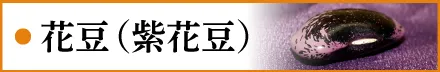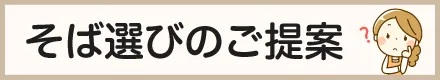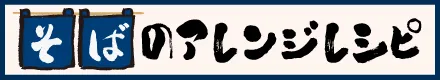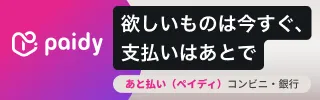そばの豆知識
そばの豆知識 - 歴史・文化編
【そばの発祥】
中国雲南省付近から世界各地へ広まったようです。長野の戸隠へは、戸隠山で修行を積む修験者たちが食料として携行していたそばの実が広まったとの一説があります。
江戸時代の書物『そば手引草』(安永四年=1775年)、『善光寺道名所図絵』(天保十四年=1843年)によると、すでに「戸隠そば」の評判は確立していたようです。
【そばの語源】
古い資料「本草和名(918年)」には「曽波牟岐」の字が当てられ「ソバムギ」と訓読しています。
ソバムギと名付けられたのは、実の形が三角形で三つの稜(よみ「そば」:「かど」の意)があるためで、角麦・稜麦の文字も当てられています。
「曽波牟岐」の「牟」の正字は「麰(よみ「ぼう」:中国語で「大麦」の意)」で、牟岐は「大麦・小麦」の総称となります。すでに栽培されていたムギと、新たに渡来したソバを区別するため、「ソバ」だけでなく「ソバムギ」と名付けたようです。
日本最古のソバの記述は「続日本紀(しょくにほんぎ・722年)」で、元正天皇の詔に、飢饉への救荒食糧としてムギとソバの栽培を命令したとされています。この詔でソバに「蕎麦」の字をあてソバムギと読んでいたようで、「蕎」だけでソバの意味を表していたようです。ソバの実をムギの実になぞらえて麦の字をつけたとも考えられます。
平安時代にはソバムギ・クロムギ(ソバの実の殻が黒褐色のため)・ソマムギと呼ばれ、室町時代以降、ソバムギが略されソバとなったようです。
【雛そば】

3月3日の桃の節句(雛祭り)、またはその翌日、雛壇に供える節句そばのこと。江戸時代中期(18世紀)には、民間にも広まっていたようです。
江戸では4日の雛納めの日にそばを供えてから雛壇を崩し、雛飾りの道具をしまいました。
そばが供えられた理由は、清めのそば・お雛様の引越しそば・長く伸びる縁起物などの諸説あるようです。
当初ふつうの二八そばが供えられていましたが、後に三色そばや五色そばとなり、市民文化の成熟とともに調度品がぜいたくさを増し、色彩の美しい変わりそばが好まれるようになりました。
ちなみに、雛そばに用いるのは五色そばだと思われがちですが、3月3日だから重三(双六でふたつのサイコロが共に3と出たときの言い方で、縁起がよいとされる)にちなむ三色そばが古式に則しているようです。なお、「雛うどん」を供える地方もあるようです。
【年越しそば】

別名「歳取りそば」「大年(おおとし)そば」「大晦日(おおつごもり)そば」などがあります。起源は明らかではありませんが、江戸時代中期の書物「眉斧日録(1756年)」には「大年蕎麦」の記述があり、すでに歳末の習わしとなっていたようです。
由来には次のような諸説があります。
「運そば」説
鎌倉時代、博多の承天寺(宋からそば製粉の方法を日本に伝えたとされる聖一国師が開山)で年末を越せない町人に「世直しそば」と称してそば餅を振る舞ったところ、翌年から町人たちに運が向いたことで習慣となった説。「運気そば」「福そば」とも言われます。
三稜(みかど:三角の意)縁起説
室町時代、関東三長者の一人・増淵民部が大晦日に無病息災を祝い、家人とそばがきを食べたものがはじまりとの説。そばの実は三稜で読みが「帝」に通ずる、あるいは三角の形状から夫婦と子供の関係にたとえられ、縁起がよいとされてきたとか。
「細く長く」の形状説
そば切りは細く長くのびることから、家運を伸ばし、寿命を延ばし、身代を永続きさせたいと縁起を担いだ説。「寿命そば(新潟県佐渡郡)」、「のびそば(越前)」とも言われました。
「切れやすい」ことからの形状説
そばは切れやすいことから、一年の苦労や厄災をきれいさっぱり切り捨てようと食べる説。「縁切りそば」「年切りそば」とも言われます。また、一年中の借金を絶ち切る意味で「借銭切り(岡山県賀陽町)」とも。どちらも残さずに食べきらないといけないそうです。
そば効能説
江戸時代の書物(「本朝食鑑(1697年)」)に蕎麦は「気を降し腸を寛し、能く腸胃の滓穢(しわい:よごれの意)積滞を錬る」とあり、そばによって体内を清めて新年を迎えるという説。ちなみに薬味のネギは、神官の禰宜(ねぎ)に通じるとの説もあるとか。
捲土重来(けんどちょうらい)説
そばは一晩風雨に晒されても、翌朝陽が射せばすぐに立ち直るということにあやかって「来年こそは」と食した説。
金運説
金銀細工師は飛び散った金銀の粉を掻き集める時にもそば粉を使うことから、そばは金を集めるという縁起で食べるようになった説。
【引越そば】
「引っ越しそば」とは、江戸時代中期から江戸を中心として行われるようになった習わしです。詳細はこちらをご覧下さい→引っ越しご挨拶用ギフト - 引っ越しそば ページ
なお、江戸時代には、「引っ越しそば」の他にも次のようなときにそばを振る舞っていたようです。
[江戸時代のそばを振る舞う風習]
棟上げそば・・・上棟式に振る舞うそば
とちりそば・・・芝居などでとちる(台詞や演技を間違えたりするなど)と、楽屋中に振る舞うそば
新板もの祝いそば・・・地本問屋で新板ものが出ると、著者や画師などの関係者を招いて振る舞うそば
新吉原敷初めそば・・・遊女が客より夜具を新調して贈られたときに祝儀として振る舞うそば
[参考文献]
・(社)日本麺類業団体連合会(1991)『そば・うどん百味百題』柴田書店
・戸隠そば商組合監修(1995)『信州・戸隠手打ちそばの技術』旭屋出版
・しまだえいこ,平尾朋子,その他(1995)『信州・味の名産と郷土料理』信濃毎日新聞社
そばの豆知識 - 技術編
【おいしいそばは「三たて」】

「三たて」とは「挽きたて・打ちたて・ゆでたて」のことで、おいしいそばの条件として使われる言葉です。
「挽きたて」とは製粉したてのことで、そば粉は時間が経つと鮮度の劣化が激しいそうです。特に理想の挽き方は「石臼挽き」。高速の機械挽きだと粉が熱を持ち、風味が飛んでしまうそうです。
「打ちたて」と「ゆでたて」もそばの劣化が早いことに起因します。ただし、小麦のつなぎを使っている場合は多少時間をかけて熟成させた方がいいようです。小麦粉に含まれるグルテンが、熟成されることで食感がよくなるためです。店頭で手打ちの実演している店でも、実演で打ったものをすぐゆでないところもあるそうです。
また、包丁切りしたばかりのそばはよくないそうです。茹で湯に入れても沈まずに浮き、うまく茹でられないのだとか。粉と水が馴染まない、こねた際に含まれてしまった空気が抜けきらない、などと考えられています。そのため、切りたてではなく、少し時間をおいてから茹でるとおいしいそばになります。
なお、「ゆでたて」はゆでたそばはすぐのびてしまうため、手際よく水切りをして素早く出さなければならないという戒めだとか。
【信州戸隠そば】石臼挽き生そば(AN)【送料無料】
そばの「三たて」をご堪能いただける生そばです。
【つなぎ】

そばのもつ独特の風味が味わえるのは、つなぎなしのそば粉100%で打ったそばですが、打ち方によってはパラパラに切れてしまうことも。
そこで歯切れをよくするため「つなぎ」が必要なのです。
「つなぎ」にはふつう小麦粉が使われますが、卵やヤマイモもよく使われます。そば屋で出されるものはおおむね「二八そば」「九一そば」と呼ばれる1〜2割の小麦粉のつなぎが入っているもの。
歯ざわりと香りのバランスが保たれるのはそば7:つなぎ3割までだそうです。
なお、JAS(日本農林規格)によると、乾麺の「そば」と呼べるものは、そば粉が3割以上(小麦粉が7割以下)のものとなります。
【信州戸隠そば】自然芋そば(G-1)
山芋粉と海藻(真布のり)をつなぎに使ったそば。普通のそばとは一味違った美味しさです。
[参考文献]
・(社)日本麺類業団体連合会(1991)『そば・うどん百味百題』柴田書店
・戸隠そば商組合監修(1995)『信州・戸隠手打ちそばの技術』旭屋出版
・しまだえいこ,平尾朋子,その他(1995)『信州・味の名産と郷土料理』信濃毎日新聞社
そばの豆知識 - 材料・道具編
【そばの種類】
そばはタデ科の植物で「普通ソバ」「ダッタンソバ」の2種類に大別されます。普段私たちが食べているのは「普通ソバ」、対する「ダッタンソバ」は別名”苦ソバ”といわれ、食べると苦みがあります。中国やヒマラヤ諸国などで栽培され、日本ではほとんど使われていません。
「普通ソバ」はさらに「夏ソバ・秋ソバ」に大別されます。夏でも秋でもほとんど変わらぬ実を結ぶ「中性種」という品種もありますが、作っている所は少ないようです。
「夏ソバ・秋ソバ」は、栽培・収穫だけでなく、味も違います。「そばは75日」といわれる程、そばは種まきから収穫までの期間が非常に短いです。
なお、戸隠では、「夏ソバ」は5月下旬〜6月下旬に種をまき、7月下旬~8月上旬には収穫されます。味・収穫量ともよいとされる「秋ソバ」は8月上旬~中旬に種を撒き、10月中旬に収穫、11月には”新そば”としてそば店に出ます。
【信州戸隠そば】生新そば(SN-30N)
新そばを石臼挽きした生そばセット。10月~1月下旬までの季節限定商品です。
【そば粉の国内生産量】

そばの消費に対し、そば粉の国内生産量は約20%程度です。輸入粉は輸送中に船倉で蒸れやすく、風味が劣るようです。(上画像はそばの実)
【信州戸隠そば】国産本十割そば(KJS-5)
国産のそば粉のみで作り上げた自慢の逸品です。
【そばの栄養成分】
そばの栄養はでんぷんが主体ですが、産地や収穫時期によって多少の違いがあります。そばは、実の内部(胚乳部が中心)と表層部(甘皮周辺)とでは、成分組成が異なります。そのため、そば粉は実の中心部から順に一~三番粉として製粉されますが、それぞれの栄養成分には違いが出ます。
殻をつけたまま挽いた挽きぐるみ(全層粉)の場合には、タンパク質を多く含みます。タンパク質を構成するアミノ酸のうちリジン(小麦粉に不足)・トリプトファン(白米に不足)に富んでいます。反対にそば粉の不足アミノ酸は小麦粉に多く含まれています。ですので、そば粉と小麦粉が混ざっているそばは、タンパク質補給の点で理にかなっています。
なお、そば粉にはビタミンA・Cはほぼ含まれていませんが、ビタミンB1・B2は米や小麦の約2倍。また、毛細血管の働きを安定・強化させるルチンが豊富です。ルチンはビタミンCと同時に摂取すると効果大だそう。さらに、腸の働きをよくする食物繊維も含んでいます。
【そば湯】

そば湯とはそばをゆでた湯のことですが、ここには栄養がたっぷりふくまれています。
そば粉に含まれるタンパク質の約半分、ビタミンB類、ルチンはいずれも水溶性のため、ゆでている間にゆで湯の中に溶け出してしまいます。タンパク質はそばの旨み成分でもあるので、栄養面だけでなく、そばを余すところなく味わうにもそば湯を飲んだ方がいいですよ。そばがきもおすすめです。(そばがき:そば粉を熱湯でこねたもので、そばねりとも言います)
そばを食べた後にそば湯を飲む風習は、まず長野・信州で始まり、江戸に広まったのだとか。なお、おそば屋さんで見かけるそば湯を入れる容器は湯桶(ゆとう)といいます(上画像は角湯桶のイメージ。丸いものは丸湯桶といいます)
【信州戸隠そば】そばがき(C-1)【まとめ買いでおトク】
熱湯を入れて混ぜるだけ! 簡単・手軽にそばがきが味わえます。
【田舎そばと更級そば】
「田舎そば」とは鬼皮(おにがわ:外側の厚く堅い皮)をむいただけで挽いた粉を使用したものです。農家が自家用に打って食べたものがルーツ。「更級そば」とはそばの実の中心に近い部分が使われ、白くてのどごしがよいのが特徴です。
【おいしいそばの代名詞「霧下そば」】

現在、そばは国内いろいろな所で栽培されていますが、なお戸隠そばが一級品とされるのは”霧下そば”といわれる良質のそばを産出しているためです。
”霧下そば”とは、本来は昼夜の気温差が激しく、霧が発生する場所でとれたそばを指します。こうした条件で育ったそばは実が締まり、タンパク質やグルテンに富んだうまいそばとなります。
長野の戸隠はまさにこの条件に当てはまり、標高1000m辺りの火山灰地帯にそば畑が広がり、夏でも霧に覆われるほど。味・香り・色も優れた霧下そばが生み出されています。
【干しそば(乾麺のそば)】
長野県は干しそば年間生産量トップ(全国30%弱)で、2位は山形県(14%)。信州産の干しそばはそば粉の含有率が多く、そば粉が40%以上含まれているものが「信州そば」として市場に出ています。(日本農林規格のJASマークはそば粉30%以上のものに認められています)
当店で販売している乾麺はこちら
十割そばや八割そば、太切りや細切りのそばなど、様々な種類のそばを取り揃えております。
【半生そば・生そばの違い】
「生そば」は、打ったままのそばを密封して冷蔵庫で1週間〜10日位保存可能です。これに対し「半生そば」とは、生そばから一定の水分を抜き、蒸気殺菌もしくは加熱殺菌して常温保存を可能にしたもの。1〜3ヶ月は日持ちするものが多いです。
当店で販売している半生そばはこちら
生そばよりも日持ちがし、それでいて生そばに近い味わいを楽しめるのが半生そばの魅力です。
【七味唐辛子】

関西では「七味」、関東では「七色(なないろ)」唐辛子と呼ばれていたようですが、現在では七味唐辛子と一般に呼ばれています。七味唐辛子はねぎや大根とともに、そばの薬味の”御三家”の一つに数えられています。
薬味というのは、風味を増し食欲をそそると同時に、毒消しの効果を併せ持っており、いわゆる日本の香辛料にあたります。こうした日本の香辛料は、目的や役目により以下のように分けられます。
青み料(ネギ、三つ葉等)、辛み料(カラシ、ワサビ、ショウガ等)、香味料(シソ、サンショウ等)、芳(こう)ばし料(ゴマ、クルミ等)、和え料(ミョウガ、タデ等)など。
これらのうち「辛み・香料・芳ばし」の三料を巧みに配合した混合香辛料が、七味唐辛子です。配合の割合によって大辛・中辛・小辛と分けられます(甘口・辛口と分ける場合もあります)。七味唐辛子の老舗三店のうちのひとつとして、長野のおなじみ『八幡屋礒五郎』は知られています。
【そばの薬味の御三家】
昔から「からみ、やくみも味のうち」といわれるように、薬味を加えて風味の増加・食欲増進に役立てていました。そばの薬味としては昔から「刻みネギ・大根おろし・七味唐辛子」が「御三家」とされています。
八幡屋礒五郎 七味唐からし(S-7)
おなじみ善光寺名物の「七味唐辛子」です。
【器】
セイロに盛るのは、一説には鉄鍋が普及する前は、水気をよく切るセイロにそばを盛って重ねて蒸したからだとか。長野の戸隠などで竹のザルを使うのは、根曲がり竹の産地で昔から竹細工が盛んで・水気を含んでも腐食しにくいからだとも言われています。
[参考文献]
・(社)日本麺類業団体連合会(1991)『そば・うどん百味百題』柴田書店
・戸隠そば商組合監修(1995)『信州・戸隠手打ちそばの技術』旭屋出版
・しまだえいこ,平尾朋子,その他(1995)『信州・味の名産と郷土料理』信濃毎日新聞社